警察は彼を「帝銀事件」の犯人だと言い、裁判所は死刑を言い渡した。でも平沢貞通は最後まで無実を叫び続けた。あなたはこの事件の真相を知っているだろうか?
1948年、東京で12人が青酸カリで毒殺された未解決事件「帝銀事件」。絵描きだった平沢は23年間も死刑囚として生き、国家に殺された男となった。
冤罪か真犯人か。70年以上経った今でも専門家の意見が分かれるこの謎。当時の捜査資料と新事実から見えてくる真相は、私たちの「司法への信頼」を根底から揺るがすものかもしれない。
では、なぜ警察は平沢を犯人と断定したのか?そこには驚くべき捜査手法の闇が隠されていた…
帝銀事件の概要

A. 事件の基本情報と発生時期
帝銀事件は1948年1月26日、東京・日本橋の帝国銀行椎名町支店で起きた大量毒殺事件です。閉店間際の午後4時頃、一人の男が「厚生省の職員」を名乗って銀行に現れました。この男は「GHQの指示で消毒作業を行う」と告げ、職員に白い粉末を溶かした液体を飲ませたんです。
「今から発生する赤痢の予防薬です」
そう言って配られた液体。でも実際には猛毒の青酸カリが入っていました。信じて飲んだ16人中12人が死亡する悲惨な結果に。戦後の混乱期、公的機関への信頼が厚かった時代ならではの犯行手口でした。
B. 犠牲者の数と事件の衝撃
その日、銀行には行員と数名の客を含め16人がいました。青酸カリ入りの液体を飲んだ結果、わずか10分ほどで苦しみ始め、最終的に12人が命を落としました。残りの4人は一部しか飲まなかったか、完全に拒否したため一命をとりとめています。
当時の日本人にとって、この事件の衝撃は計り知れないものでした。特に犯行の手口が巧妙だったことと、大量殺人という点で社会に恐怖を与えました。
「戦争は終わったのに、なぜこんな残酷なことが…」
人々はそう思いました。新聞各紙は連日大きく報道し、日本中が犯人逮捕を待ち望みました。戦後まもない時期に起きた凶悪犯罪として、多くの人の記憶に刻まれることになったんです。
C. 当時の社会背景と日本の戦後状況
帝銀事件が起きた1948年は、日本が敗戦からわずか2年半後。社会全体が混乱の真っただ中にありました。
GHQによる占領政策が進み、人々は新しい指示や命令に従うことに慣れていました。戦時中の統制経済から抜け出せておらず、官公庁や公的機関からの指示は絶対的なものとして受け入れられていたんです。
食糧難や住宅不足、インフレなど、生活は苦しく、伝染病の流行も珍しくありませんでした。特に赤痢などの消化器系伝染病は頻発しており、「赤痢の予防」という言葉は人々の警戒心を解くのに十分だったんです。
犯人はこうした社会状況を巧みに利用しました。「厚生省」「GHQ」という権威を騙り、「赤痢予防」という緊急性を演出することで、疑いの余地を与えなかったのです。
この事件は単なる犯罪としてだけでなく、占領下の日本社会が抱えていた脆弱性や権威への過度の従順さを浮き彫りにしました。戦後の混乱と不安が生み出した悲劇と言えるでしょう。
平沢貞通の人物像

経歴と人となり
平沢貞通は1914年、岩手県の貧しい農家に生まれました。幼少期から苦労の連続で、満足な教育も受けられないまま育ちました。貧困から抜け出すため、15歳で上京し、靴職人として生計を立てることになります。
手先が器用だった平沢は、その技術を活かして独立。「平和靴店」という自分の店を持つまでになりました。家族思いの一面もあり、妻と3人の子どもとともに、質素ながらも平穏な生活を送っていたとされています。
周囲の評判は「几帳面で真面目」「口数は少ないが、穏やかな性格」。特に靴の修理に関しては妥協を許さない職人気質で、地域では信頼される存在でした。ただ、神経質な面があり、周囲との深い交流は少なかったようです。
逮捕までの経緯
帝銀事件が起きた1948年1月26日、平沢は自宅で靴の修理をしていたと主張しています。事件から7ヶ月以上経った8月21日、突然GHQの指示で逮捕されました。
逮捕に至るまで、捜査線上に平沢の名前が上がることはありませんでした。警察は当初、別の容疑者を追っていましたが、行き詰まりを見せていました。そんな中、ある匿名の密告が平沢を指名。これが決定打となったのです。
逮捕時、平沢は何の疑いもなく警察署に出向き、自分が犯人ではないと確信していました。しかし、その足で拘留され、長時間の取り調べが始まったのです。
犯人として浮上した理由
平沢が犯人として浮上した理由はいくつかあります。まず、彼が医療関係の知識を持っていると見なされた点。靴職人として使用する薬品に関する知識が、青酸カリを扱える能力と結びつけられました。
また、目撃者の証言と平沢の外見が「似ている」とされたことも大きかったです。「痩せた体型」「眼鏡」「医師のような印象」という曖昧な特徴が平沢に当てはめられました。
さらに、平沢が取り調べ中に見せた態度も不利に働きました。疲労と精神的圧迫から混乱し、時に矛盾した供述をしたことが「犯罪者の心理」と解釈されてしまったのです。
平沢の主張と無実の訴え
平沢は一貫して無実を訴え続けました。「事件当日は自宅で仕事をしていた」というアリバイを主張し、家族もこれを証言しています。
取り調べでは激しい拷問を受けたと後に証言しています。「自白するまで帰れない」「家族も逮捕する」などの脅しに晒され、40日以上も睡眠を満足に取れない状態が続いたと言います。
最終的に「もう耐えられない」と虚偽の自白をしたと平沢は主張。その後、法廷では自白を撤回し、「拷問によって無理やり署名させられた」と訴えました。
死刑が確定した後も、平沢は手紙や面会を通じて自分の無実を訴え続けました。「国家によって殺される」と悟りながらも、最後まで真実を明らかにしようとした姿勢は、多くの支援者の心を動かしました。
裁判過程と問題点

A. 取調べにおける不正行為の疑惑
平沢貞通の取調べ過程には、今日の法的基準からみれば許されない多くの問題があった。特に目立つのは、警察による連日24時間以上に及ぶ厳しい取調べだ。睡眠不足と精神的圧迫の中で、平沢は最終的に「自白」に追い込まれた。
当時の取調官が使った手法は?
- 食事制限
- 睡眠妨害
- 家族との面会制限
- 精神的威圧
平沢自身が後に証言したように、「もう何でもいいから早く楽にしてほしい」という一心で虚偽の自白をしたというのだ。昭和の初期、被疑者の権利なんて言葉すら定着していなかった時代の話だ。
B. 証拠の信頼性と矛盾点
平沢事件の証拠を見ると、矛盾だらけで驚く。まず、指紋証拠が一切ない。現場に残された足跡も平沢のものと一致しなかった。
毒物に関しても疑問が山積み。犯行に使用された青酸カリの入手経路が特定できず、平沢の自宅や所持品からは毒物の痕跡すら見つからなかった。
さらに決定的なのは、アリバイ証言だ。犯行時刻に平沢が別の場所にいたという複数の目撃証言があったにもかかわらず、裁判所はこれを無視した。
C. 裁判の進行と判決
裁判は1948年から始まり、一審で死刑判決。しかし、証拠の不十分さから高裁は差し戻しを命じた。再審理の結果も死刑。最高裁も1955年に上告を棄却し、死刑が確定した。
平沢の弁護団は必死に闘ったが、当時の司法システムでは「自白」の重みが異常に大きかった。証拠より自白が優先される時代だったのだ。
D. 再審請求の歴史
平沢の死後も、再審請求は続いた。彼の妻・千代は夫の無実を信じ、死ぬまで再審請求活動を続けた。その後も支援者たちによる再審請求は継続し、現在も7次にわたる再審請求が行われている。
しかし司法は頑なだ。新証拠の提出や科学的検証の進歩があっても、再審開始決定には至っていない。
E. 法的観点からの問題提起
平沢事件は日本の刑事司法制度の根本的欠陥を露呈させた。
現代の視点から見ると:
- 取調べの可視化がなかった
- 弁護人の立会権が制限されていた
- 証拠開示制度が不十分だった
- 自白偏重の捜査・裁判
この事件は「人質司法」の典型例として、今も法学者や人権活動家から批判の対象となっている。冤罪事件の教訓として、取調べの全過程録画など、現代の刑事訴訟法改革の原動力にもなっている。
平沢事件の裁判過程は、時代の制約を考慮しても、正義とは程遠いものだった。一人の男が国家権力によって「殺された」という事実は、今も私たちに重い問いを投げかけている。
「国家に殺された」とされる背景

GHQ占領下の司法制度の実態
戦後の日本はGHQによる占領下で、司法制度も大きく変わりました。表向きは民主化という名目でしたが、実態は複雑です。
当時の裁判は今とは全く違いました。GHQの監視下で行われ、「迅速な正義」が優先されていました。証拠よりも自白が重視され、取調べでの自白強要は日常茶飯事。平沢貞通の裁判もこの環境で行われたんです。
驚くべきことに、当時の裁判官たちはGHQの意向を無視できませんでした。「民主的な判決」を出すよう圧力がかかり、特に社会的注目を集める事件では、その傾向が強かったんです。帝銀事件は当時のメディアで大々的に報じられ、犯人逮捕と処罰を求める世論が形成されていました。
平沢の裁判記録を見ると、現代の法律家なら誰でも首を傾げるような手続き上の問題点が山積みです。弁護側の証人申請が不当に却下されたり、検察側に有利な証拠だけが採用されたりと、今では考えられない不公正さがありました。
政治的背景と冤罪の可能性
冷戦初期のこの時代、日本国内では共産主義への恐怖が広がっていました。帝銀事件の犯行手法が毒物使用だったことから、「組織的テロ」の可能性が取り沙汰されました。
平沢は元軍人で、当時の政府にとって「処罰すべき過去の遺物」と見なされていた可能性があります。彼の経歴が冤罪を作り出す動機になったという見方は無視できません。
専門家たちは、真犯人は別にいたという説を支持する証拠を多数指摘しています。犯行時の目撃証言と平沢の外見の不一致、毒物に関する専門知識の欠如など、重大な矛盾点が放置されたままでした。
当時の国家権力と司法の関係
占領期の日本では、司法は完全に独立していたとは言えませんでした。国家権力、特に警察と検察は密接に連携し、GHQの意向を反映した判決を出すことが暗黙の了解だったんです。
裁判官たちは「国家の安定」を優先するよう教育されていました。疑わしきは罰せずではなく、社会的影響を考慮した判決が下されることもありました。平沢の場合、無罪にすることは当時の社会秩序を揺るがすリスクがあると判断された可能性が高いです。
処刑決定に至った政治的圧力
平沢の死刑執行は異例の速さで行われました。通常、最高裁判決から執行までには相当の時間がかかりますが、彼の場合はわずか数週間でした。
この背景には、当時の日本政府がGHQからの独立を目前に控え、「治安維持能力」を示す必要があったという指摘があります。未解決のまま残される可能性のあった大事件を「解決済み」とするため、平沢の処刑が急がれたのです。
複数の元司法関係者が匿名で語ったところによれば、平沢の再審請求が認められる可能性を恐れた政治家たちの意向が、法務省を通じて伝えられていたとのこと。これは正に「国家による殺人」と呼べる構図です。
未解決の真相
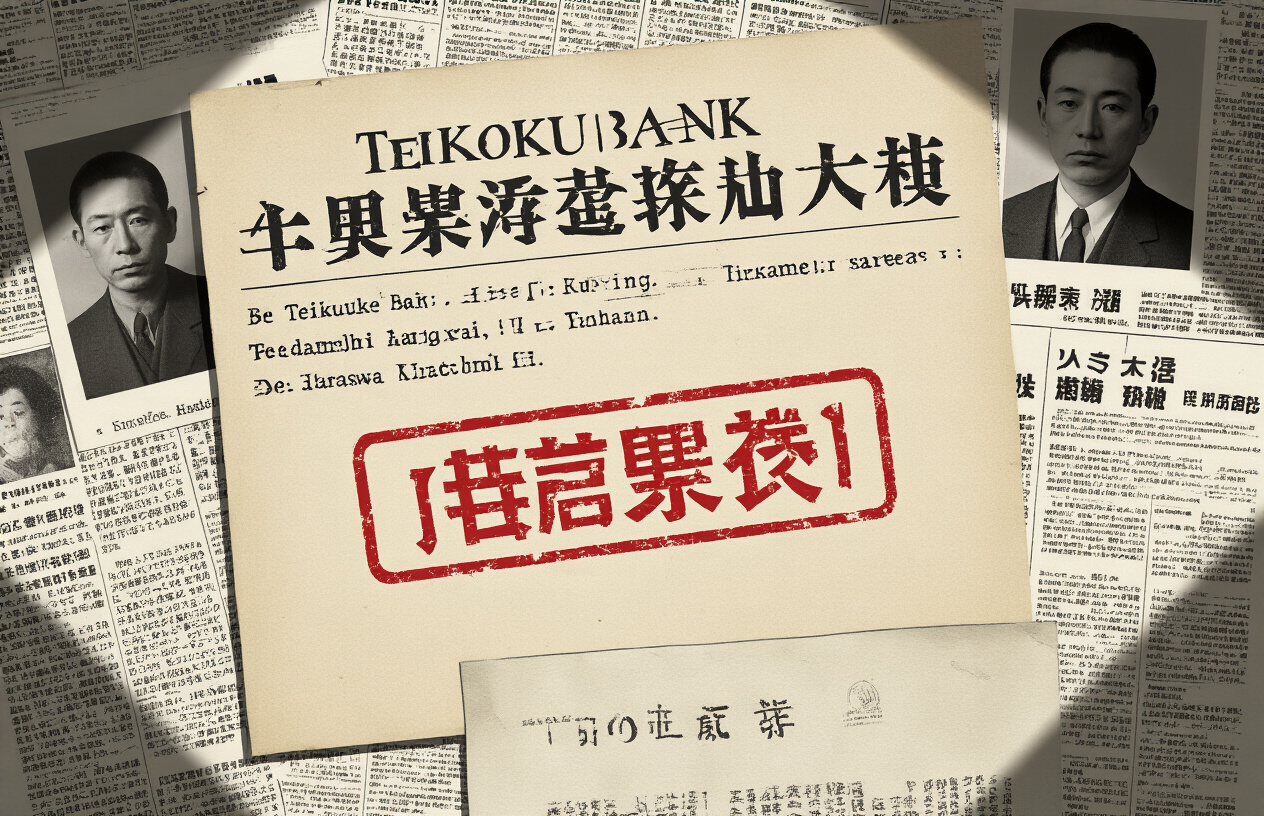
事件の謎と残された疑問点
帝銀事件から70年以上経った今でも、多くの謎が残されています。平沢貞通の有罪判決を受け入れられない理由は、証拠の不自然さにあります。
まず、目撃者の証言が食い違いだらけ。犯人の身長、体格、声の特徴、そして服装まで、証言はバラバラでした。平沢の体型と合わない証言も多く、「小太りの中年男性」という描写は平沢の痩せた体格とは一致しません。
毒物の謎も深まるばかり。犯行に使われた青酸化合物の入手経路は今も不明です。平沢が勤務していた軍の研究所では確かに毒物を扱っていましたが、彼自身がそれを持ち出した証拠はありません。警察は平沢の自宅を何度も捜索しましたが、毒物製造の痕跡すら見つかりませんでした。
「死刑囚のアリバイ」も重要な疑問点です。当日、平沢は新宿の飲み屋にいたと主張。複数の目撃者がこれを裏付けていますが、裁判所はなぜかこれを認めませんでした。
別の犯人説と有力な仮説
帝銀事件の真犯人については、いくつかの説が浮上しています。
最も有力なのは「GHQ関与説」。当時のアメリカ占領軍が何らかの形で関わっていたという説です。占領政策への批判をそらすため、または日本の警察機構を掌握するための「見せしめ」として事件が利用されたという見方もあります。
「旧日本軍関係者説」も根強く、敗戦後に隠された軍事機密や資金をめぐる争いが背景にあったとされています。毒物の専門知識を持つ軍関係者が犯行に及んだ可能性は高いでしょう。
もう一つ興味深いのは「共犯者説」。単独犯ではなく複数の犯人がいたという仮説です。これなら目撃証言の食い違いも説明がつきます。
新たに発見された証拠や証言
近年、帝銀事件に新たな光を当てる資料が次々と見つかっています。
2010年代に入って公開された裁判記録や警察の内部文書からは、平沢の自白が拷問によって引き出された可能性が高まっています。当時の取調べ方法はすさまじく、食事や睡眠を与えないなど現代では考えられない手法が日常的でした。
また、事件当時を知る銀行員の子どもたちからの証言も集まっています。「父は犯人の姿を見たが、平沢とは全く違うと言っていた」という証言は複数あります。
専門家による事件の再検証
法医学や犯罪心理学の進歩により、帝銀事件の再検証も進んでいます。
現代の法医学者によれば、当時の毒物検査は不十分で、青酸カリと断定するには証拠が足りないとされています。犯行に使われた毒物の正体すら、実は確定していないのです。
犯罪心理学者からは「平沢の自白には典型的な虚偽自白のパターンがある」との指摘も。拷問や誘導尋問によって生み出された自白には、実際の犯行とは整合しない矛盾点が必ず含まれるといいます。
事件から長い時間が経過した今、帝銀事件は「冤罪の可能性が高い未解決事件」として再評価されています。平沢貞通の名誉回復を求める声も年々大きくなっているのです。
現代社会への影響と教訓

冤罪防止と司法制度改革への示唆
帝銀事件は日本の刑事司法制度の根本的な欠陥を露呈させました。平沢貞通の事例は、自白偏重主義の危険性を如実に示しています。当時の取調べでは、長時間の尋問や心理的圧力が日常的に行われ、その結果として信頼性の低い自白が生まれました。
「自白は証拠の女王」と言われた時代は終わりました。現在では取調べの録音・録画制度(可視化)が導入されていますが、これは平沢の悲劇が現代に残した大きな教訓の一つです。
弁護側の証拠へのアクセスも限られていました。平沢の弁護人は重要な証拠を十分に検討する機会がなく、これが公平な裁判を妨げました。現在の証拠開示制度の改善は、この事件から学んだ結果と言えるでしょう。
戦後日本の闇と歴史的教訓
帝銀事件は単なる刑事事件ではなく、戦後日本社会の深い闇を映し出す鏡でした。GHQ占領下での捜査は、政治的圧力に左右され、日本の自主性が制限された状況で進められました。
占領政策の影響で、当局は迅速な犯人逮捕を迫られ、結果として捜査の公正さより「結果」が優先されました。平沢事件は、権力が強い圧力を持つ状況下での司法の脆弱性を教えています。
誰も真犯人を追及せず、冤罪の可能性がありながら死刑が執行された事実は、司法が時に「真実」より「秩序維持」を優先する危険性を示しています。
平沢貞通の遺族と支援者の活動
平沢の死後も、遺族や支援者たちは真実究明の闘いを続けてきました。彼の娘である平沢きみは生涯をかけて父の無実を訴え、再審請求を続けました。
支援団体「帝銀事件の真相を究明する会」は、新証拠の発掘や世論喚起に努め、この事件を風化させない活動を続けています。彼らの粘り強い活動は、時に司法の壁に阻まれながらも、冤罪問題への社会的関心を維持する原動力となっています。
遺族の苦しみは、冤罪事件の「第二の被害」として認識されるべきものです。真実が明らかにならないまま何十年も経過する苦痛は計り知れません。
歴史的事件としての帝銀事件の位置づけ
帝銀事件は日本の戦後史における重要な転換点として位置づけられます。この事件は単なる未解決事件ではなく、日本の司法制度や社会のあり方に疑問を投げかけ続ける「生きた歴史」です。
多くの研究者や作家が帝銀事件を題材にした作品を発表し、松本清張の『或る「小倉日記」伝』をはじめとする文学作品は、司法の問題点を広く世に知らしめました。
70年以上経った今でも議論が続くこの事件は、真実の追求と司法正義の重要性を訴え続けています。平沢貞通の人生は、権力の前に立つ個人の脆弱さと、それでも真実を求め続ける人間の尊厳を象徴しているのです。
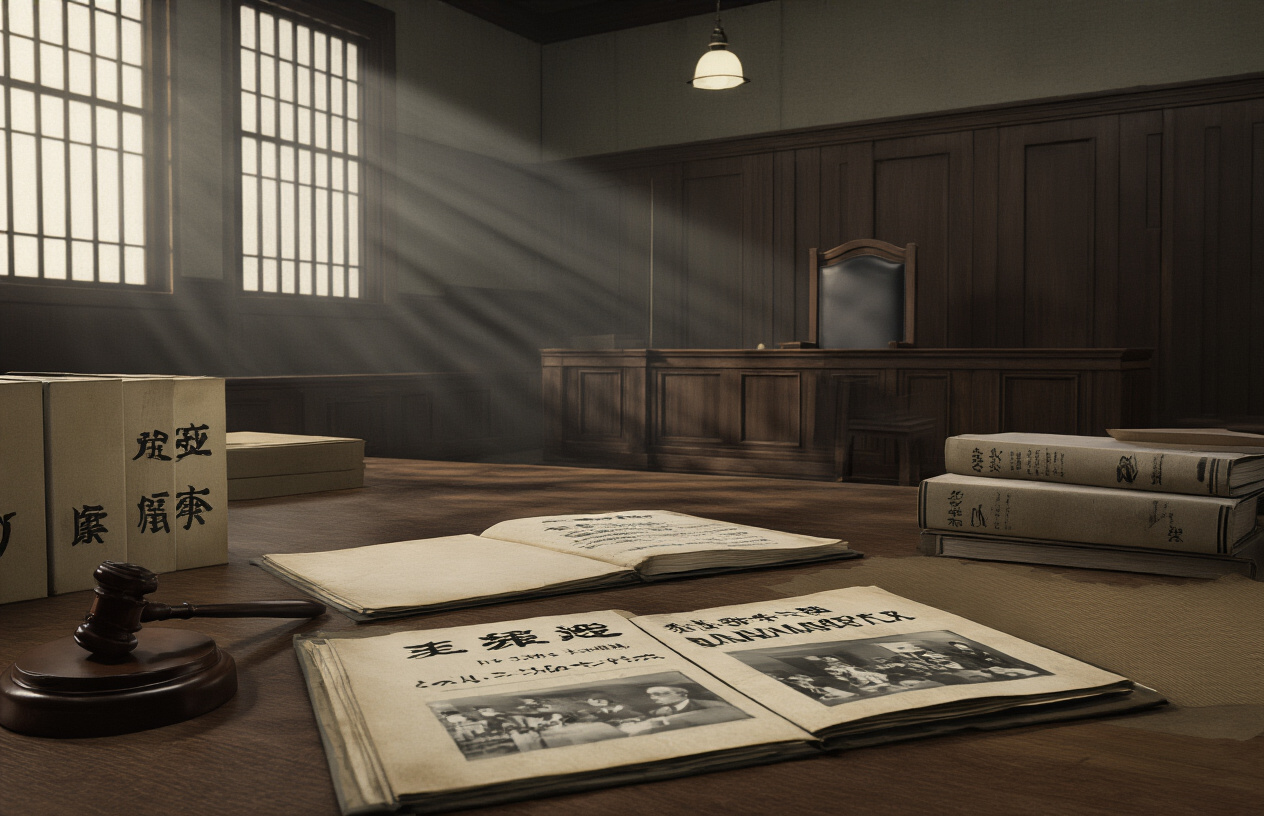
帝銀事件は日本の戦後史に大きな影を落とした未解決事件であり、平沢貞通という一人の男性の人生を奪った。彼の裁判過程には多くの問題点が指摘され、「国家に殺された」と評される背景には、当時の社会情勢や司法制度の欠陥が浮き彫りになっている。真相は今なお明らかになっていないが、この事件が問いかける司法の公正さと人権の尊重の重要性は色あせていない。
帝銀事件は単なる過去の出来事ではなく、現代社会にも重要な教訓を与えている。冤罪の可能性、証拠の扱い方、そして何より国家権力と個人の関係性について深く考えさせられる。私たちは平沢貞通の悲劇から学び、同じ過ちを繰り返さないために司法制度の透明性と公正さを常に追求していくべきだろう。



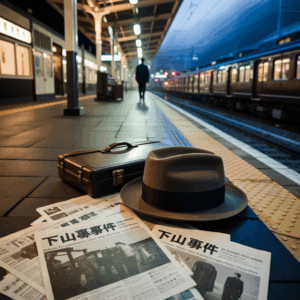



コメント
コメント一覧 (1件)
冤罪か?真相は闇に葬られた。